|
2010,11,29, Monday
モバイルプリンターのポラロイドPoGoを使っていますが、RICOH GRⅡで使用したときにはコツが必要です。
何も考えずにUSBケーブルでPoGoとGRⅡを接続しただけでは、きちんと認識しません。 ①ポラロイドPoGoとRICOH GRⅡどちらも電源を切った状態でUSBケーブルを接続する ②ポラロイドPoGoの電験をON ③素早くADJ.ボタンを押す(この時ADJ.ボタンを押してくださいと表示される前に押す。かなり早く…素早くADJ.ボタンを押すのが難しければPoGoの電源をONする前から押しておく) この操作を失敗するとカメラがフリーズしたり、プリンタを認識しません。 GRシリーズ以外もRICOHのカメラはそうなのかな。。。 これって仕様というより不具合のような気もしますが、ファームウェアのアップデートで対処するつもりもなさそうですね。PoGoとの組み合わせで利用する人が極端に少ないのかもしれません。 とりあえず僕にとっては不具合にしか思えませんが。。。 Poraroid PoGo ■ プリントしてシェア。約5 x 7.5センチの縁なしカラー写真を1分足らずでプリント。 ■ ZINK Imaging開発のZINK® Zero Ink®プリント技術で、インクを使わずにプリント。 ■ モバイルに最適。ポケットサイズのス 用紙が小さいのでノートに貼れてとっても便利ですが、仕上がりはキレイとは言えません ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=502 |
| etc | 12:15 AM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,26, Friday
今年も高大連携先の大阪府立布施北高等学校のデュアルシステム専門コース発表会へ行ってきました。
高大連携の授業で制作したプレゼンテーションを使っての発表や、毎週一回行っている実習先企業での体験を寸劇にしたものなど非常に工夫された発表会でした。 布施北高等学校でおこなっているデュアルシステム専門コースは、全国で唯一普通科高校でカリキュラムの中に企業での実習をおこなうシステムで、週一回学校へは登校せず実習先の企業で職業体験を年間通しておこなうという、大変めづらしい制度をとりいれています。 週一回の企業での実習と、3年生は本学に週一回通学して2コマの授業を大学内で受講しています。 大学内でおこなう高大連携授業では、高等学校の正規の卒業単位の中に含まれ、高等学校の商業科目のひとつとして単位認定されています。 先週の金曜日にプレゼンの練習をしたときには、まだ完成とは程遠いものでしたが、今日はかなり完成度の高いプレゼントして見ることができました。 実は先週おこなったプレゼン練習を見て僕は少し不安になっていたのですが、良いプレゼンができていて安心しました。 僕自身が彼等と同じ年齢だった頃はとてもじゃないけどプレゼンなんてできるものではありませんでしたが、そこは企業での体験でコミュニケーション能力の養われている彼等は強かった… 毎年多くの連携を引き受けている企業の方々や保護者の皆さんがたくさん、この発表を見に来られている中堂々としたプレゼンテーションに驚かされます。 来年度、本学で僕の授業を受講する高校生の皆さんは70人だと聞いています。 授業の方法を少し変えないとできないのでちょっと来年度に向けて考えてみます。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=501 |
| etc | 11:53 PM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,17, Wednesday
今日は朝から近隣の中学校から本学へ職業体験に来ている生徒さん6名を情報教育センターで受け入れました。情報教育センターでの仕事体験は午前中だけですが、生徒の皆さんは熱心に取り組んでくれました。
まず始めは学内に3教室あるPC教室の1つのソフトウェアアップデートの作業をおこなってもらいました。 この教室はリモートアップデートできない教室で、PC個々にアップデートしなければなりません。なぜアップデートということをしなければいけないのかなどを簡単に説明して作業が始まりました。 一斉にネットワークに接続してアップデートさせるためアップデートが始まるとしばらく時間がかかります。 その間、情報教育センターに移動し学内で撮った広報用の写真のストックの一部を、Webページなどで利用するためにリサイズの作業です。 これも撮ったカメラはまちまちなので写真によってサイズが違います。 すべての写真を横巾200ピクセルにリサイズして保存しなおしの作業をおこなってもらいました。 今日の職業体験の写真も含まれているため、その写真は後日大学Webページにアップします。 リサイズの作業が終わると、また教室に戻りアップデートの確認です。 ちょっと中学生には解説の話は少し難しかったかなと思いますが、熱心に聞いてくれました。 考えて見れば僕の中学時代はこのような職業体験はありませんでした。もう30年も昔の話しですが。。。 当時の僕は成績は無残なもので、将来どんな仕事に就きたいかということは考えてはいませんでした。やってみたい仕事はありましたがこの成績じゃ無理だなと自分で諦めていたところもあり… 今では、中学生も高校生も、大学生でも職業体験をおこない様々な仕事をみることも可能です。考えて見れば羨ましい。 最近の子どもは無気力だなどとよく聞きますが、変わったのは子どもが先ではなく大人社会です。大人社会の反映が子どもの社会です。 大人が変わらなければ子どもの社会は変わりません。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=500 |
| etc | 09:37 PM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,17, Wednesday
韓国では、来春(新学期は3月から始まる)から、すべての小中学校において、英語、国語、数学の3科目についてデジタル教科書導入を義務化する。さらに2013年には、生徒1人1台のタブレット端末導入を目指す。
(http://bit.ly/c5ojLz Wired Vision 2010/10/04) 日本でもデジタル教科書については様々なところで議論されています。ipadの登場以来その議論はますます盛んになっているようには見えますが、 現場の多くの教員がそれを望んでいるかというと、そうでもありません。 ネット上ではかなり熱い議論も交わされてはいるのですが、コンピュータやネットを自在に使う教員とそうでない教員の間にはかなりの温度差があるんじゃないかと思います。 デジタル教科書ではリッチコンテンツを使うことにより、紙の教科書にはない動画や音声も埋め込むことができ、教科書としての表現力は確かに非常に高くなります。 だから授業は面白くなるかというと、そうではありません。初めは今までにない驚きや感動があるかもしれませんが、それはすぐに飽きられてしまいます。 デジタル教科書導入については様々な課題が残されています。 インターネットにも接続するのであれば、各教室の無線LAN環境も全ての教室に配置する必要があります。 そして、充電設備。これを作るのには結構なコストも必要です。 以前、高等学校教員時代に情報コースを担当していて、クラス全員に卒業まで一人1台のノートPCを配布して自宅や教室、そして授業でも利用していましたが、故障などの対応も大変でした。 1学年1クラスだけのコースでも大変だったのですから、これが全校生徒となると考えただけでもぞっとします。 ハードウェアやインフラ整備だけでも問題山積ですが、もっと重要なことはデジタル教科書を教育ツールとして全ての教員が使いこなせるのかといいうことです。 デジタル教科書は単なるツールであり、授業の主体は生徒であり、教師です。様々なコンテンツを使い今まで以上に楽しい授業が設計できるのかどうか。 現職の教員についても全教員が対応できるかどうか不安な面がありますが、これから教員となる学生を育てる教員養成大学でもそういった対応はほとんどできていません。 教育工学関係の科目で取り扱う場面はありますが、時間的にはあまり無いのが現状です。 教員養成大学などでもっとデジタル教科書についての検証実験や実際に学習ツール、教科書としてもっと多くの大学が取り入れてみて様々な問題をクリアする必要があります。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=499 |
| etc | 12:04 AM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,15, Monday
学生がやってきて、「先生、CD入らないんですけどぉ…」
そう言われて何のことかわからず、「自習室PCのCDドライブ壊れてるの?」と聞くと、 「違う、USB」と答えるので、 「?・・・USBが認識しないの?」と聞くと 「CDがUSBに入らないの…」 結局学生は自分の買ってきたCDをUSBメモリスティックに入れたいということだった。 おそらくUSBミュージックプレーヤーにmp3音源として入れたいようで、大学の自習室PCでそれができないのかという質問のようだ。 大学の自習室PCではセキュリティ上そういったことは出来ないことを説明し、自宅のPCでやりなさい。と伝えた。 こちらが、相手の意図する質問内容を把握するためのかなりの努力をしないといけない。 伝えるための表現力が少なすぎるのだ。 言語というものは、時代が変わるに連れて長い年月をかけて変わっていくものですが、こういった言語の変化とは明らかに違い、語彙力の低下による伝達能力の低下です。 日本の大学生全般に言えることですが、書く力はもとより言葉で表現する力が低下しています。 日常生活で長文を読むということ自体が少なくなっています。レポート課題はインターネットで調べればピンポイントで解答が得られ、何冊も参考文献を読むということも少なくなっています。 文章を読むということは、その文章から得られる直接的な知識だけではなく、日頃自分では使わない表現方法を自分の頭の中にインプットできるチャンスです。これは、教科書や参考文献だけではなく、小説を読んだ時にも様々な表現方法が自然と身についてくるものです。 気のあった友人だけと話すのではなく、世代を超えていろんな人と話すこと。これが本当に大事です。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=498 |
| etc | 09:02 PM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,14, Sunday
午前中に少し仕事をして、今日は書店巡り。
3冊の本を購入。 『メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い』 坂根厳夫 (著) 『メディア文化論—メディアを学ぶ人のための15話』 吉見 俊哉 (著) 『資本主義と自由 (日経BPクラシックス) 』ミルトン・フリードマン (著), 村井 章子 (翻訳) なかなかまとまった時間がなくて、買ったまま読めずに山積みになってる本がたくさんありますが、少しでも時間をつくって読みたいと思います。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=497 |
| books | 08:08 PM | comments (x) | trackback (x) | |
|
2010,11,09, Tuesday
「プログラミン」は、プログラムを通じて、子どもたちに創ることの楽しさと、方法論を提供することを目的とした、ウェブサイトということで文科省から公開されている。これが結構いろんなことができて面白い。
プログラミングをしようとすると、PCにコンパイラなどのツールが必要になりますがWeb上でおこなえるのでインターネットにさえつながっている環境であればいつでも学習できます。用意された絵や自分で書いた絵を動かしたり、遊びながら物事の処理手順を考える練習ができ、意外と大人も楽しめます。 プログラミン | 文部科学省 http://www.mext.go.jp/programin/ 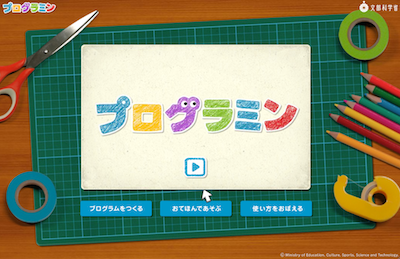 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室
| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=496 |
| etc | 03:35 PM | comments (x) | trackback (x) | |
















